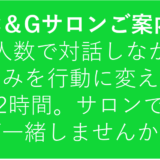みなさまこんにちは。
先日、万博で日本館を訪ねました。
テーマは「循環」。
日本で引き継がれてきた自然観と美意識を
体現した展示になっています。
特に、日本が自然環境に対応してきた
方法として、ある種“ゆるく構えておく”
ことの重要性が謳われていたのが
印象的です。
例えば「流れ橋」と言うものがあります。
川が増水した際、橋梁部と上部の板部が
分離し、板部が流される仕組みの橋です。
全てをガッチリ固めて作ってしまうと
川が増水した際に壊滅的な被害を
被ってしまう可能性があるのですが、
一部を手放すことで、基礎部分を
守り、かつ再生もしやすくしています。
この“ゆるく構えておく”と言う考え方。
今後の気候変動の社会でも参考になる
考え方ですし、人に対しても参考に
なる考えなのではと思いました。
ガチガチに自分の中での形やルールを決める
ほど、「想定外の出来事」が起こった時に
対応が難しくなったり時間がかかったり
するものですよね。
今は正解のない時代。
自分でガッチリ決めた「べき論」に
従うことでかえって苦しくなって
しまうこともあります。
実際今、組織には色々な人がいて、
意見の対立は以前に比べると起こりやすく
なっています。
ディスカッションをしていて、
なんでそんなこと言うの?はぁ?
と思うことも少なくないかもしれません。
ではこういう状況の時にはどうしたらいい
のでしょうか。
例えば、
自分の中での「こうでなければならない」を
少し緩める。相手には相手の理由があるかも
しれない、と自分の頑なな心を緩めてみる。
しかしもちろん、自分の軸や芯は大事に
守る、というやり方もいいかもしれません。
話の過程で白黒はっきりつけたり、
勝ち負けで考えたりするということでは
なく、議論に余白を持たせる・・・
自分が譲れないところは大切に
しつつも、グレーゾーンはそのままに
しておくことも、時に有効では
ないでしょうか。
少し時間をかけて落とし所を探る
ことでお互いの信頼も大事にする
・・・そんな議論があってもいいと
思います。
みなさまはいかがでしょうか。
議論や打ち合わせの進め方やチームづくり
のご相談も、サロンではしていただけます。
定期開催しております。次回のご案内は
以下をご覧くださいませ。
それでは皆様、暑さももう少し(と信じたい)、
皆様素敵な1日をお過ごしください。